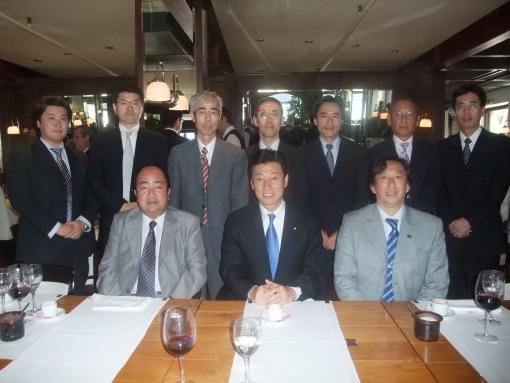BLOG
南米諸国・米国・英国出張(その①)「アルゼンチン編」
1.2月中旬、南米諸国、米国、英国に出張した。機中で4泊し、7日間で世界を回るという強行日程であったが、大変有意義な出張であった。順次ご報告したい。
2.まず、アルゼンチン。約15年ぶりの訪問である。ブエノスアイレスは、かつて南米のパリと呼ばれただけに、街中は先進国のような雰囲気で、古い倉庫群もカフェなどに生まれ変わり(写真①)、大統領府()や独立記念塔()は、ブエノスアイレスの目抜き通りであるフロリダ通りのつきあたりと真ん中に位置する。雨上がりなのか、運河(?)の水は濁っているが、向こう側ではマンションなどの開発が進んでいる()。
3.ブエノスアイレスでは、1913年に地下鉄を建設し()、実は、我が国は地下鉄建設の際にブエノスアイレスまで視察に行っている。しかし、その後の世界の変化・経済情勢の大変化で、今では、東京丸の内線の古い車両をブエノスアイレスの地下鉄用に譲り渡している。乗ってみると、確かに丸の内線に乗っているかのような錯覚になる()。日本もいつか同じことになるのではと心配にもなる。
4.昼食を共にした日系企業の方々()は、異口同音に「アルゼンチンは、潜在力・可能性の大きな国だが、政策が安定しない」、「石油、天然ガスなどの資源も豊富なのに、投資が進まない」など、大きな発展の可能性は認めつつも、国の舵取りへの不安も口にしていた。それでも日系2世のリカルド・ハラさんは、農業で大成功をおさめており、日本企業との連携を模索していた。米国、ブラジルと並ぶ農業輸出国であり、まだまだ未開の農地も限りなくあると言う。是非、食料基地としての投資を後押ししたい。
5.面談したフェルナンデス経済・財政大臣とは、日本への公的債務1600億円を含む約7000億円の債務返済問題について意見交換を行った()。昨年後半からの世界的金融危機で、「返済が難しくなった」と言うが、それまでの数年間、安定成長をしていただけに、その時から少しずつ返し始めておけばよかったのである。ラテンの国らしいと言えばその通りだが…。それでも、G20のメンバーであり、金融危機への対応やWTO交渉における保護主義への懸念について、突っ込んだ議論を行った。両国の連携は確認しつつも、IMF(国際通貨基金)のやり方(米国流)に対する不満や、自国の農産品輸出に課税することの正当性に言及された。
6.カメロン・エネルギー長官及びボエル国家原子力委員会委員長とは、原子力の平和利用、新エネルギーの導入、地球温暖化問題への取組みについて、意見交換()。同国の原子力委員会では、日本で研修を受けた約20人の方が勤務しており、日本の取組みへの感謝を述べられた。やはり、日本は「原子力の平和利用」のモデル国家として評価されており、そのことを自負しながら、世界に範を示す気構えが大事だ。
7.タチェッティ筆頭外務副大臣、キアラディア外務副大臣とは、債務問題、WTO、原子力協力、地デジの日本方式導入、などなど、数多くのテーマについて意見交換を行った(、⑪)。
特にキアラディア外務副大臣は、昨年来日された時に意見交換しており(2008年11月4日活動報告参照)、元駐日大使の親日家で、時間が足りなくなるほど話し込んだ。特に、地デジの日本方式の導入について、ブエノスアイレスの中心部でワンセグの実験が行われており、副大臣はじめ局長など幹部の前で携帯電話の画面で映像を紹介したところ、大変喜んで頂いた。日本方式の採用の決定に向けて、あと一歩のところまで来ていることを確認した次第である。
8.そして、アルゼンチンの次の目的地、隣国のウルグアイに行くために空港に向かうが、その途中にあるNECソフト開発センターに立ち寄る()。昨年9月29日のオープニングには、キルチネル大統領も来賓として出席してくれている。大統領府の監視・警備システムなどを手掛けており、ソフト人材のレベルは極めて高いものがあるとお聞きした。アルゼンチンは農業大国のイメージで、意外な感じがした。知っているつもりでも、我々がまだまだ知らないことも多いのである。勉強しなければならないことは多い。世界の国は多い(193ヶ国!!)。
2.まず、アルゼンチン。約15年ぶりの訪問である。ブエノスアイレスは、かつて南米のパリと呼ばれただけに、街中は先進国のような雰囲気で、古い倉庫群もカフェなどに生まれ変わり(写真①)、大統領府()や独立記念塔()は、ブエノスアイレスの目抜き通りであるフロリダ通りのつきあたりと真ん中に位置する。雨上がりなのか、運河(?)の水は濁っているが、向こう側ではマンションなどの開発が進んでいる()。
3.ブエノスアイレスでは、1913年に地下鉄を建設し()、実は、我が国は地下鉄建設の際にブエノスアイレスまで視察に行っている。しかし、その後の世界の変化・経済情勢の大変化で、今では、東京丸の内線の古い車両をブエノスアイレスの地下鉄用に譲り渡している。乗ってみると、確かに丸の内線に乗っているかのような錯覚になる()。日本もいつか同じことになるのではと心配にもなる。
4.昼食を共にした日系企業の方々()は、異口同音に「アルゼンチンは、潜在力・可能性の大きな国だが、政策が安定しない」、「石油、天然ガスなどの資源も豊富なのに、投資が進まない」など、大きな発展の可能性は認めつつも、国の舵取りへの不安も口にしていた。それでも日系2世のリカルド・ハラさんは、農業で大成功をおさめており、日本企業との連携を模索していた。米国、ブラジルと並ぶ農業輸出国であり、まだまだ未開の農地も限りなくあると言う。是非、食料基地としての投資を後押ししたい。
5.面談したフェルナンデス経済・財政大臣とは、日本への公的債務1600億円を含む約7000億円の債務返済問題について意見交換を行った()。昨年後半からの世界的金融危機で、「返済が難しくなった」と言うが、それまでの数年間、安定成長をしていただけに、その時から少しずつ返し始めておけばよかったのである。ラテンの国らしいと言えばその通りだが…。それでも、G20のメンバーであり、金融危機への対応やWTO交渉における保護主義への懸念について、突っ込んだ議論を行った。両国の連携は確認しつつも、IMF(国際通貨基金)のやり方(米国流)に対する不満や、自国の農産品輸出に課税することの正当性に言及された。
6.カメロン・エネルギー長官及びボエル国家原子力委員会委員長とは、原子力の平和利用、新エネルギーの導入、地球温暖化問題への取組みについて、意見交換()。同国の原子力委員会では、日本で研修を受けた約20人の方が勤務しており、日本の取組みへの感謝を述べられた。やはり、日本は「原子力の平和利用」のモデル国家として評価されており、そのことを自負しながら、世界に範を示す気構えが大事だ。
7.タチェッティ筆頭外務副大臣、キアラディア外務副大臣とは、債務問題、WTO、原子力協力、地デジの日本方式導入、などなど、数多くのテーマについて意見交換を行った(、⑪)。
特にキアラディア外務副大臣は、昨年来日された時に意見交換しており(2008年11月4日活動報告参照)、元駐日大使の親日家で、時間が足りなくなるほど話し込んだ。特に、地デジの日本方式の導入について、ブエノスアイレスの中心部でワンセグの実験が行われており、副大臣はじめ局長など幹部の前で携帯電話の画面で映像を紹介したところ、大変喜んで頂いた。日本方式の採用の決定に向けて、あと一歩のところまで来ていることを確認した次第である。
8.そして、アルゼンチンの次の目的地、隣国のウルグアイに行くために空港に向かうが、その途中にあるNECソフト開発センターに立ち寄る()。昨年9月29日のオープニングには、キルチネル大統領も来賓として出席してくれている。大統領府の監視・警備システムなどを手掛けており、ソフト人材のレベルは極めて高いものがあるとお聞きした。アルゼンチンは農業大国のイメージで、意外な感じがした。知っているつもりでも、我々がまだまだ知らないことも多いのである。勉強しなければならないことは多い。世界の国は多い(193ヶ国!!)。